 |
|
 |
指定有形文化財「夷灊神社」です。
所在する大多喜町は夷隅郡(いすみぐん)に
ありますが、神社は夷灊(いしみ)と読みます。 |
|
本殿内部西面内法貫に寄進者名がありました。
それによると「貞享2年(1685年)」とあり
おおよそ329年前の建造物となります。 |
 |
|
 |
その91年後、安永5年(1776年)に拝殿と幣殿の
建て直しが行なわれたという墨書きが
ありました。 |
|
また9年後の天明5年(1785年)の本殿屋根替えの
棟札がある。杮葺き(こけらぶき)の葺直し
とあるが、その間にも数回の葺直しをした模様。 |
 |
|
 |
文化3年(1806年)に拝殿をはじめ、
文政7年(1824年)にすべて銅板へ葺き替え
しているようです。 |
|
そのまた59年後の明治16年(1883年)に
大規模改修が行われ屋根の葺き替えを
行なっていると想定されます。 |
 |
|
 |
約131年の時を経て今回の改修工事が
行なわれました。歴史ある建造物改修に
携わる事が出来て非常に光栄に思います。 |
|
いよいよ工事の準備に入ります。 |
 |
|
 |
各所において大きな工事から細かい工事まで
ありますので、足場の掛け方ひとつで
進行速度が大きく変わる大事な作業です。 |
|
棟の解体。 |
 |
|
 |
銅板は虫食いのように損傷していましたが
この箇所の下地は大変良い状況でした。 |
|
棟下地も解体していきます。 |
 |
|
 |
銅板が紙のように薄くなっている箇所や、下地の
損傷によって銅板と野地面の空洞化が起こり
長期間の雨や風での変形・凹凸が各所に見える。 |
|
屋根面の解体状況。 |
 |
|
 |
| 屋根面の解体状況。 |
|
解体中に当時の杮葺きが出現しました。
100年以上前からカバー工法があったのだと
実感した瞬間です。杮葺きとは薄い木材を
重ねて敷き詰める葺き方です。 |
 |
|
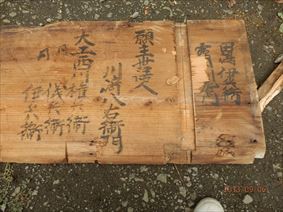 |
本殿・幣殿・拝殿等の取り合い谷部は
このように損傷が激しい状況でした。 |
|
当時の職人の銘が記された貴重なもの |
 |
|
 |
| しっかり養生をし、下地改修に備えます |
|
大勢の大工が入り各所で作業しますが、
まずやりやすい小さい箇所から行います。 |
 |
|
 |
有形文化財ですので、基本は全交換でなく
「補修と復元」が第一前提です。
悪い所は同じ形で復元、一部損傷はその箇所のみ
下地を入れ補修をします。 |
|
解体してみると母屋桁が不足していたり
大きな補強が必要になる作業が多くあり、
その都度関係者で打ち合わせを
重ねて改修しました。 |
 |
|
 |
よって当初の予定から大幅に変更し、破風板を補強
小屋組・垂木・飛檐垂木などを全面交換しました。 |
|
社寺仏閣は技術的難易度が高く、
すべての職人が出来る作業ではありません。 |
 |
|
 |
| 野地施工まであと少しです! |
|
野地施工が始まりました。 |
 |
|
 |
| 完成です。 |
|
垂木類もすべて当時のように交換しました。 |
 |
|
 |
| 屋根葺き組も加工に入ってます。 |
|
蓑甲の加工です。 |
 |
|
 |
銅板一文字葺きを施工してます。
銅板は季節によって伸縮が大きいので
葺く場合もそれらを頭に置いて
調整しながら葺いていきます。 |
|
取り合いが多いので、施工箇所も面毎に
行なっていきます。 |
 |
|
 |
| 足場を組みながら慎重に作業します。 |
|
向拝千鳥破風の下地処理です。
この形に沿って熟練の職人がすべて
手作りで銅板を加工していきます。 |
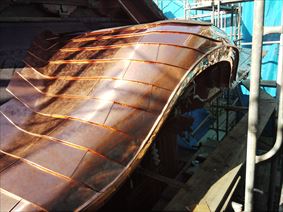 |
|
 |
馳の接合箇所から曲がり具合まで
すべて「魅せる」よう計算して
張っていきます。 |
|
この丸みは銅板技術ももちろんですが
大工の下地施工がすべてといっても
過言ではありません。 |
 |
|
 |
銅板は酸化が速いので、このように施工時期に
よって異なりますが、すぐに同色になります。 |
|
谷の曲がり方と蓑甲の曲がり具合が
絶妙ですね。 |
 |
|
 |
飾り職人も各種飾りの加工に入っています。
写真は千木(ちぎ)の加工です。 |
|
鬼型を描き、それを基に銅板を切り出し、
鬼を作っていきます。今では鬼を作る職人も
また鬼をつける建造物も減ってきました。 |
 |
|
 |
弊社工場の半分が夷灊神社の飾りで一杯に
なりました。飾り次第で社寺仏閣の完成度が
大きく変わる非常に大事な作業です。 |
|
千木や鬼につける家紋類です。
家紋は種類が20,000種以上ありますので
プレスでなく職人が手造りで叩いて、
擦って仕上げていきます。 |
 |
|
 |
| 大棟の加工 |
|
千木を取り付けるステンレス製ピース。
意匠を考え、それも銅板で包みました。 |
 |
|
 |
|
|
いよいよ棟乗せです |
 |
|
 |
| 数人がかりで取付します。 |
|
棟など仕上げ部分はすべて熟練職人が
監修し指示を出していきます。 |
 |
|
 |
| 棟の銅板枠にはあとで家紋が入ります。 |
|
ハマグリと呼ばれる部材です。
|
 |
|
 |
足場も解体しすべて完成しました。
131年前の状態へ戻りました。
完成したのに戻ってしまうのは
非常に不思議な感覚ですね。 |
|
この屋根がまた、長い月日を経て
数十年後に改修される日まで大切な
有形文化財を雨・風から守ります。 |
 |
|
この屋根改修工事は木工事含むすべての
板金工事まで一括で受注・施工をしました。
ホームページに載せ切れないほどの写真と
資料があります。
よって一部を抜粋して省略・掲載しています。
この神社は自由に拝観できますので
ぜひ大多喜町へお越しの際は
立ち寄って見て下さい。 |
夷灊神社は前記の通り、古い歴史があり
境内には西南戦争や日清戦争を始めとする
戦没者の表忠碑や明治初期にコレラ撲滅に
力を注ぎ殉職した警察官の招魂碑などがあります。
|
|
|